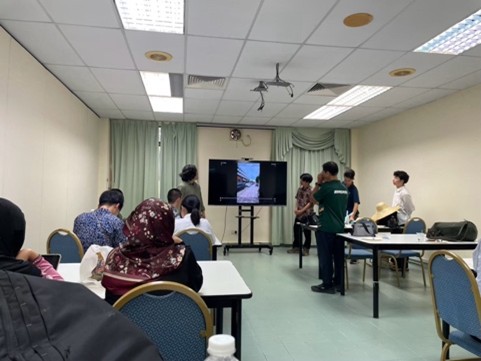2024年度 マレーシア海外自然環境実習報告書
掲載日:2025.08.08
2024年2月から3月、マレーシアの海外自然環境実習に参加した学生の報告書です。ぜひご覧ください。
マレーシア海外自然環境実習報告書
環境共生学類3年(派遣時2年) 松浦 佳澄(Kasumi Matsuura)
1.はじめに
私は、東南アジアの文化や自然環境に関心があったものの、それはイメージに留まるものでした。今回、特に開発途上国での暮らしや環境との関わり方を自分の目で見て体感してみたいと思い、この実習に参加しました。ほかにも、私は動物園や水族館の様々な動物を見るのが好きなので、いつかジャングルに暮らす野生動物の本来の姿を自分の目で見てみたいという個人的な夢もあり、それが実現できる機会であったことも大きな動機となりました。
今回の実習ではペナン、コタキナバル、KOPELの3箇所を中心に活動し、様々な体験をしました。
2.五感で学ぶペナンの多様性
実習の前半ではペナン島に滞在し、バタフライファーム、トロピカルフルーツファーム、ザ・ハビタットなどを訪れました。バタフライファームでは、室内に自然に近い環境が再現され、多くの蝶をはじめとする昆虫を間近で観察することができました。またザ・ハビタットでは、キャノピーウォークから熱帯雨林の多様な生態系を体感できると同時に、自然への影響を最小限に抑える設計が印象的でした。こうした施設では、普段は出会えない多種多様な植物や昆虫、爬虫類、動物たちと直接触れ合うことができ、貴重な体験となりました。日本とは異なる展示方法や魅せ方を通じて、こうした展示や観光が環境に与える影響についても考えるきっかけとなり、観光と環境保全のバランスについて新たな視点を得ることができました。
文化的な面では、ニョニャ・ババと呼ばれる華人とマレー人の混合文化に関する建物や、インド系、タイ系の寺院など、多様な宗教や民族が共存するマレーシア独特の街並みや雰囲気を味わうことができました。今回の実習では現地でのコミュニケーションのために英語を少し学習してから現地へ向かいました。私の英語は拙いものでしたが、現地の方に話しかけると丁寧に耳を傾けてくれ、言葉以上に「伝えたい」「理解したい」という姿勢の大切さを感じました。
食文化も非常に豊かで、現地のマレー料理に加え、タイ系、インド系、中華系の料理など、幅広い食事を楽しむことができました。こういった食事の多様性は、マレーシアがこれまで培ってきた多様性を反映するもので、そういった面でも現地の歴史や文化を体感できました。特に本格的な飲茶や、スパイスの効いた中華料理など、日本ではなかなか味わえないものが多く、毎日の食事が新鮮で楽しみのひとつになっていました。
また、マレーシアでは歩道に歩行者用の信号があまり無いので、道路を車の合間を縫って渡るという経験をしたことも印象に残っています。日本では横断歩道のないところで渡ることはほとんどなかったので、最初は戸惑いながら立ち尽くしていましたが、数日もすると現地の人のようにタイミングを見てスッと渡れるようになり、小さなことながら自分の適応力に少し誇らしい気持ちになりました。
3.コタキナバルで得た新たな視点
次にペナンから飛行機に3時間ほど乗りコタキナバルへ移動しました。コタキナバルでは、サバ大学(UMS)での講義や学生との交流がありました。UMSの先生方からは、熱帯雨林の生態系や地域の環境問題についてのお話を伺いました。これまでの授業では主に日本の自然環境に関するものが多かったので、東南アジアの熱帯雨林での自然環境問題に関する講義など、今までとは異なる視点やアプローチを知ることができました。
また、UMSの学生におすすめしてもらった床屋に行き、髪を切ってもらうという体験もしました。英語が通じる割合はペナンより少なめで最初は少し緊張しましたが、翻訳アプリを使うことで現地の人とのやりとりや雰囲気を楽しむことができ、思い出深い経験になりました。
4.KOPELで感じた自然と文化
実習の後半では、コタキナバルから7時間ほどバスに乗りKOPELへ移動しました。KOPELとはバトゥプティ村という村全体でエコツーリズムを行っている場所であり、ここではホームステイやネイチャーキャンプなどの体験や、植林やリバークルーズなどの活動を行いました。KOPELでは、念願だったテングザルを実際に見ることができたほか、オラウータンやサイチョウ、ジャコウネコなどの野生動物にも出会うことができました。
ホームステイでは、ちょうどラマダンの期間にあたっていたため、ムスリムの家族のもとで断食の様子や文化について知ることができました。ムスリムがラマダン中に唯一食べられる乾燥させたデーツという果物を一緒に食べてみたところ、思っていたよりもずっと美味しく、自分の食に対する見方が大きく変わりました。
ネイチャーキャンプでは「水曜どうでしょう」のマレーシア編で泊まっていたブンブンと似た施設に宿泊しました。キャンプ中はインターネットが通じず、夜は一緒に来たメンバーとテーブルを囲い話をしたり、自然の音を聞きながら眠ったりと、普段の生活では味わえないような時間を過ごすことができました。雨の中でのリバークルーズや、汗をかきながら植えた木の苗が数時間後にはゾウに食べられてしまったという出来事など、予想外のハプニングも含めてすべてが貴重な経験となりました。
また、コタキナバルからKOPELへ向かうその道中で景色を見ていると、ほとんどがパームヤシの農園で埋め尽くされていました。これまで授業で聞いていたパームヤシに関する環境問題を実際に自分の目で見たことで、この問題に対するその深刻さと現実を強く感じました。先輩の解説もあり、ただ風景を見るだけではなくそれが環境に与える影響についても深く考えることができました。
5.おわりに:実習を通して得たこと
今回の実習を通して、自分には無理だと思っていたことのほとんどが実際に挑戦してみると意外とできるということに気づきました。特に食事に関しては、エスニック料理が苦手だと思い込んでいましたが、ほとんど問題なく美味しく食べることができ、自分の適応力に驚きました。また、どこでもしっかりと寝れることや一緒に行ったメンバーの中で誰よりもお腹が強いということもわかり、自分のタフさに気づくことが出来ました。
一方で、未知のことに対してはじめから尻込みしてしまう自分の姿勢にも気づきました。現地の人ともっと積極的に関わることもできたと思います。こうした反省も含めて、自分の成長の余地を見つけられたことが、この実習の大きな成果だと感じています。
想像だけではわからないことが、実際に体験してみると大きく印象が変わることを、今回の実習を通して強く実感しました。環境問題にしても文化にしても、「知識として知っていること」と「実際に体験して理解すること」には大きな差があります。だからこそ、これからも未知のことに臆せず挑戦し、新しい自分と出会い続けたいと思います。
機会があればまたKOPELを訪れて、今度はもっと積極的に現地の人と関わり、さらに深い学びと経験を得たいです。
訪問先
エントピア(バタフライファーム) https://www.entopia.com/
トロピカルフルーツファーム https://tropicalfruitfarm.com.my/
ザ・ハビタット https://thehabitat.my/
KOPEL https://www.kopelkinabatangan.com/